障害があり、収入も少ない暮らしの中では、すべてを手に入れることはできません。
体調に波があり、働ける時間も限られている──。
そういう現実の中で、僕は「何を大事にするか」「何を削るか」を意識的に選ぶ必要がありました。
この記事では、僕が“生活の軸”をどうやって決めたのか、そしてそれが心の安定やお金の使い方にどう影響したかについてまとめてみます。
目次
「全部やろうとすると、全部つらくなる」と気づいた
かつての僕は、「普通の生活に追いつきたい」という気持ちで、あれもこれも無理に抱えようとしていました。
でも、収入は月9万円。
体調が悪ければ1日寝込むこともある。
その現実に気づいたとき、「すべてに応えようとするほど、自分が消耗していく」と実感しました。
軸を決めると、“迷い”が減った
そこで僕は、暮らしの中で「これは守る」「これは後回しでいい」という基準をつくりました。
たとえば…
- 家賃と通院費は、何よりも優先する
- 食費は削りすぎず、体調を崩さない範囲で節約
- 娯楽や人付き合いは“無理のない範囲で”がルール
このように自分なりの“生活の軸”を持つようになってから、出費や行動の判断がラクになりました。
生活の軸=「自分を守るための最小限」
僕の生活の軸は、次の3つです:
1. 住む場所を安定させること
家を失えば、体も心も回復できないと考えています。
2. 体調を崩さないこと
無理な労働や節約で体を壊せば、回復に時間もお金もかかります。
3. 心が折れないように、小さな安心を毎日に入れること
たとえば、コーヒー1杯、お気に入りの本、誰かとの会話など。
これらを最優先にし、他の出費や行動はその次。
「軸がぶれなければ、生活が傾いても立て直せる」と思えるようになりました。
軸を決めてよかったこと
- 支出の優先順位がはっきりして、家計管理がラクになった
- 無理な人づきあいや見栄を張る出費を減らせた
- 「やらなくていいこと」が明確になり、心の負担が減った
- 小さな満足や安心を大切にできるようになった
まとめ
- 生活に制限があるからこそ、“軸”を持つことが大切
- 「全部やる」は無理。「自分を守るために何を大事にするか」を選ぶ
- 軸があると、日々の迷いや出費のブレが少なくなる
- 自分にとっての軸は、「住」「体」「心」の3本柱だった
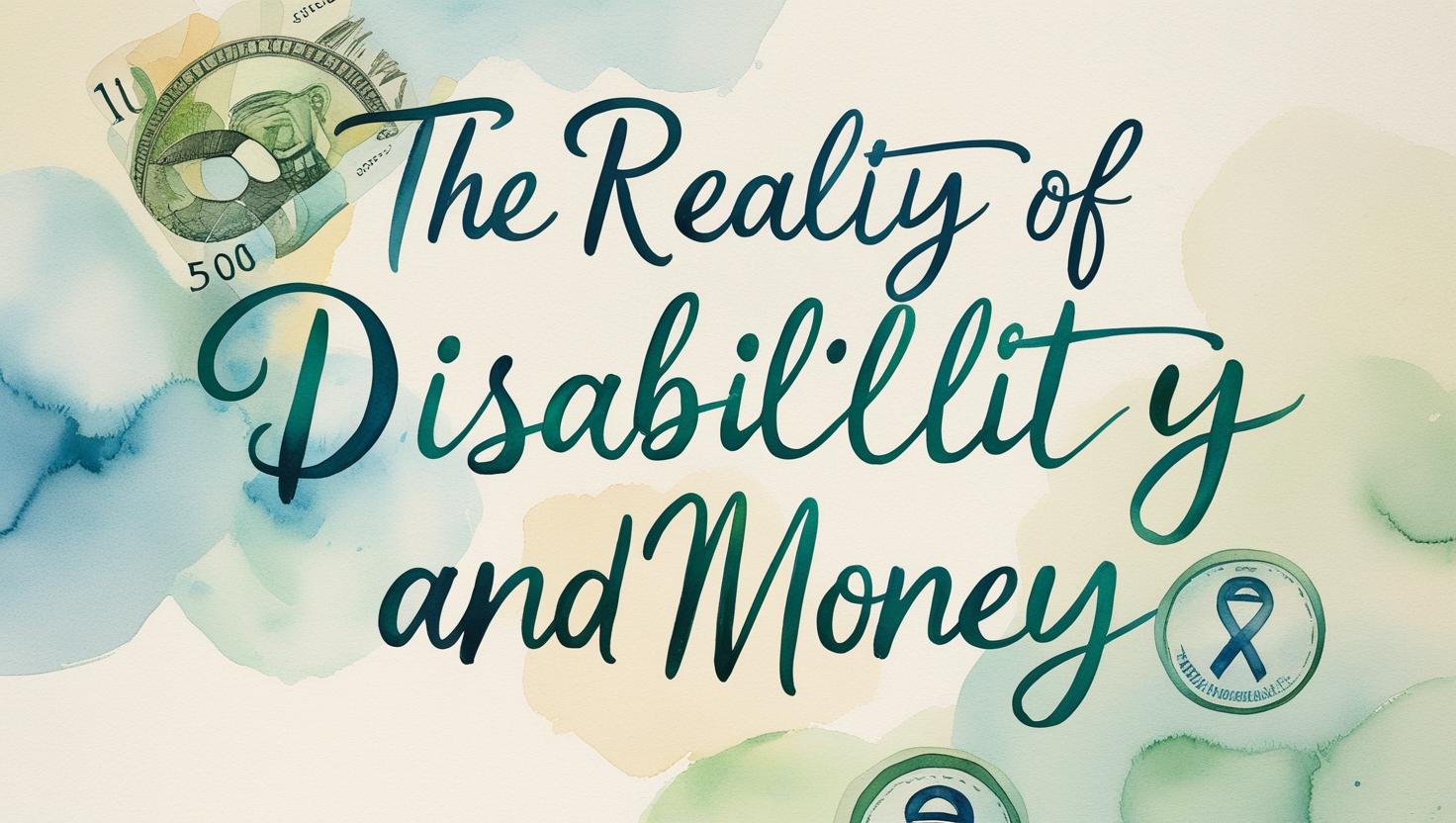

コメント