制度に守られていると、「これで大丈夫」と安心する気持ちが出てきます。
でも、その一方でふとこんな疑問も浮かびます。
「このまま、支援がある前提で流されていいんだろうか?」
「制度があるから、自分で考えることをサボってないか?」
そんな葛藤を感じた時期がありました。
今回は、制度に頼りつつも「暮らしを自分で整える意識」をどう持ち続けているかを、僕なりの視点でまとめてみます。
目次
制度があること=自動的に暮らしが整う、ではない
障害者手帳や医療費助成、A型事業所。
これらのおかげで生活の「最低ライン」は守られています。
でも、暮らし全体をどう形作るかは、やっぱり自分の役割。
- 何を食べるか
- いつ寝て、いつ起きるか
- どこまで働くか、何にお金を使うか
それらを考え続けることが、「支援のある生活」を生きるうえでの軸になっています。
1. 「制度で守られていること」と「自分で整えること」を分けて考える
たとえば、医療費助成で病院に通えているのは制度のおかげ。
でも、その通院のスケジュールをどう管理するか、薬の飲み忘れを防ぐにはどうするかは、自分の工夫次第です。
同じように、A型で働けているのは支援のおかげ。
でも、生活リズムを整えたり、疲れたときのケアは自分で調整する必要があります。
制度は「環境を整える道具」、生活の“中身”は自分の責任。
その意識を持つことで、自分らしさが保たれています。
2. 「自分なりのルール」を決める
暮らしを自分で整えるには、自分に合った“マイルール”を持つことが役立ちました。
- 朝起きたらまず窓を開ける
- 曜日ごとにやることをざっくり決めておく
- 疲れたら、無理せず寝る
他人から見たら些細でも、こうしたルールがあるだけで、「制度の枠の中に流されるだけの生活」から抜け出せます。
3. 「支援に依存しすぎない工夫」は未来への準備になる
制度はありがたいけれど、いつどう変わるかわかりません。
そのときのために、「制度に100%頼らない暮らし方の感覚」も、少しずつ育てておくことが大事だと感じています。
- 節約や生活コストを見直す
- 情報を自分で調べてみる
- 支援者に任せすぎず、自分で動いてみる
それがいざという時の“備え”にもなっています。
4. 自分の生活を「仕組み化」して負担を減らす
体調が不安定な日もあるからこそ、生活を仕組みで回せるように整えておくことも意識しています。
- 食事は買い置きで数パターンを固定
- 毎日の記録はテンプレート化
- お金の管理は表を使って自動化
「整える」とは、がんばることではなく、“考えなくて済む仕組み”をつくることでもあります。
まとめ
- 制度がある生活でも、暮らしをどう作るかは自分の役割
- 制度が整えてくれるのは「土台」、中身は自分で考える必要がある
- 自分に合ったマイルールや生活の工夫を持つことで、主体性が保たれる
- 支援に頼りすぎない意識は、将来への備えにもつながる
- 無理せず生活を仕組み化することで、暮らしの安定を自分の力で守れる
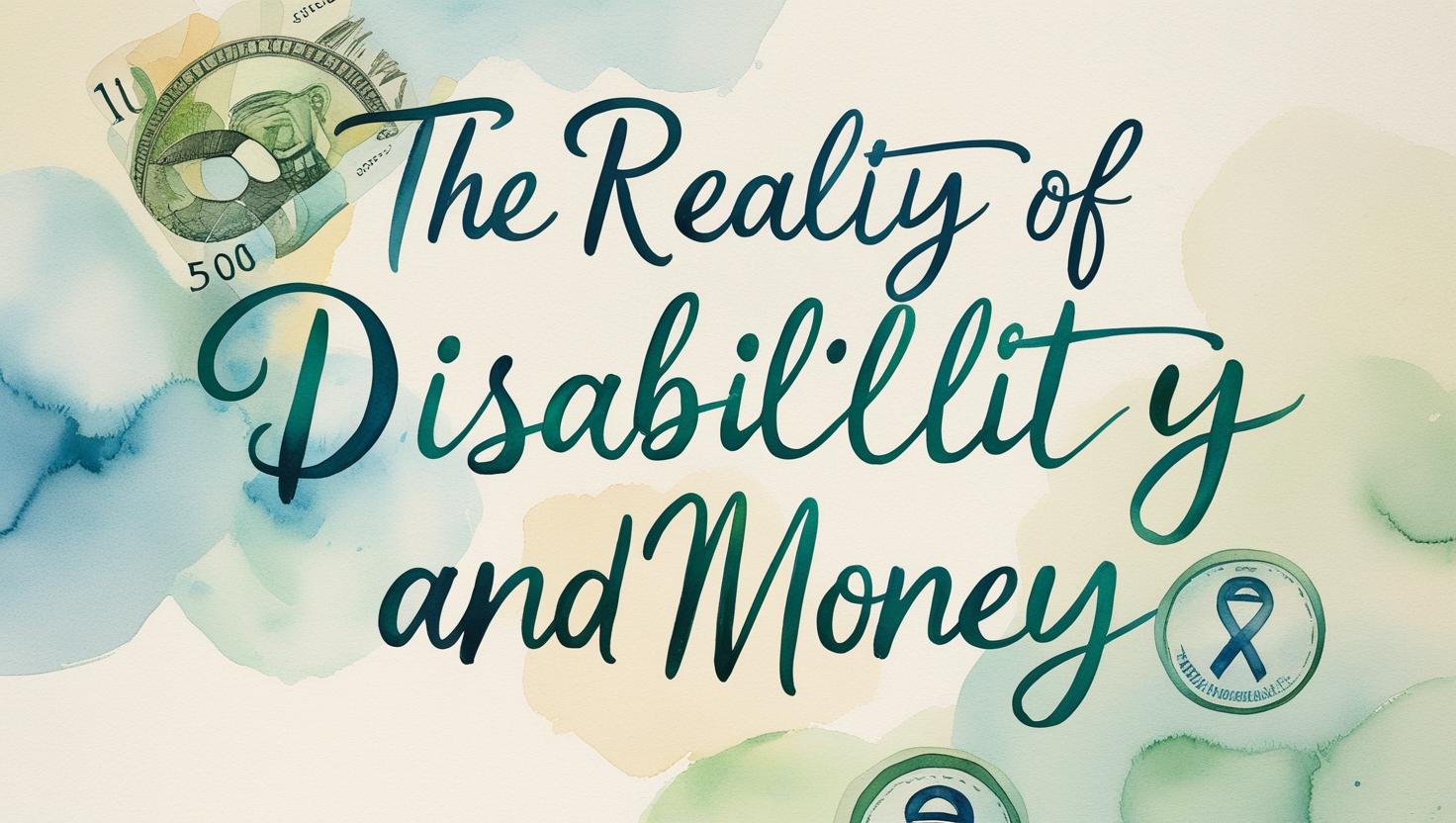

コメント